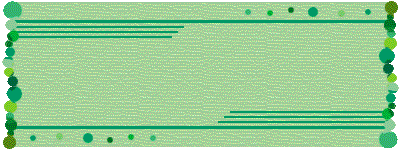 白い藤の挽歌
白い藤の挽歌父はその木をシオジと言いましたから、私もシオジと言いましょう。植物図鑑をひもといてみれば、ヤチダモと言うのが本当
のようです。いずれにしろ落葉樹の大木で、広い庭のすみの塀際に一本、塀の外の細い流れと、それに沿った小道を間
に置いてもう一本、たくさんの枝と枝を重ね合わせるようにして立っていました。塀の内側のほうの木の根元には古い藤
の木があり、二本のシオジのこずえのあたりまでその太い蔓をはいのぼらせていました。毎年五月頃になると、二尺にも
なんなんとする白い花房を風に舞わせ、夏は重なり合った藤の葉とシオジの葉が広い庭に木漏れ日をさざめかせました。
秋にはまた一夜のうちに庭中を覆うほどの落ち葉に驚き、残された大きなナタマメのような実莢が初冬の空に時折パチン
とはじけると、平べったい種子が屋根に落ちて、乾いた音をたてるのでした。
二十二歳でこの古い家に嫁いできた母には、それからの二十三年の生涯に一度として嫁でない日はありませんでした。
六人の子供(私たち兄妹)をもうけましたけれど、祖父母は昔ながらのきびしさ、それに小姑である叔母たちが四人も一緒
に暮らしていましたから、心をひらいて明るい顔になれる日があったかどうかわかりません。旧制の高等女学校を出て、こ
の大きな家、地主の長男に嫁いで、女中や下男を幾人も使っておりましたのに、なぜかいつも荒れた手をしておりました。
三番目に生まれた女の子だった私がまだ五つか六つくらいのとき、「母さんの手はざらざらして気持ちが悪い」と言ったこ
とがありました。すると母は静かに「柔らかくて細い白い指のことを白魚のような指と言うけれど、それはただきれいだと言
うだけで美しいと言うのではないのですよ。一生懸命働いて、ひびやあかぎれが出来た手は、見た目はわるいけれども、
人の心を映して一番美しい手・ビューティフルハンドというんですよ。その手の持ち主こそ本当の美しい心の持ち主なのだ
から、それを恥じてはいけないのよ。」と言ったのでした。まだ幼くて、この言葉の意味など解れるわけはない私でしたの
に、ざらざらした手で私の柔らかくてすべすべした手をなでながら、母はこの言葉をもしかしたら自分自身に言い聞かせて
いたのではないのでしょうか。その時の母のしぐさと、ビューティフィルハンドと言う英語を私は忘れませんでした。
弟を産んで二年目の正月、母は子宮癌で入院しました。今で言えば子宮体癌でしょう。既に手術も出来ないくらいに進行
していて、死が近づくのを待つばかりになっていたのでした。入院することになったとき、母は病院からすっかり疲れて帰
ってきて、炬燵に横たわりました。中学三年生になったばかりの私に「癌だって・・・」と言って聞かせました。付き添ってい
った叔母が父たちとひそひそと前の座敷で顔を寄せて話し合ってたのですが、私はその言葉がどれほどの意味をもっい
るかを知らずに聞いたのです。入院して治療すればよくなると思っていたのです。まだ四十五歳の母でした。
戦後の食糧事情や交通事情最悪の時期でしたので、中学三年生の私は、秋田市の病院まで、母と付き添っていた姉の
為に毎週三時間もかけて米を背負って運んだのでした。行くたびに母の顔は暗くなり、血の気のない濁った顔色になって
いくのがわかるのでした。
そのころ、叔父(母の弟)が婚約して婚約指輪を贈ることにしたからと言って、祖母が小さなダイヤモンドを入れた指輪を
持ってきて見せたことがありました。すっかり痩せてしまい、掌のふくらみすらなくなっていた母の手は、かつてのビューテ
ィフルハンドの哀しみとは違った悲しさを持っていました。祖母の見せた指輪をそっと自分の薬指にはめて、あおむけにな
ったまま顔の前に手をかかげました。すると火箸のようになってしまった母の指と指輪が触れてかたかたと微かな音をた
てるようでした。「私はこんな美しい指輪をするような生活ができなかった。美しい思い出を持つことも出来なかった。六人
の子もまだ小さいし、このまま死んでしまうのはいやだ。この美しい指輪はもう私には似合わないけれど、死にたくない、
死ぬのはいやだ。みんなと笑いあって楽しい生活をしないで死ぬのはいやだ。あまりにも私が可哀想・・・。」小さなダイア
モンドがちらちらとあかりをうつして輝くのをじっと見つめて、母はしばらく黙っていました。祖母の方にゆっくりと目を向け
るとゆっくりと一言だけ「わたし、やせたなぁ。」と呟いたのでした。そして閉じた目尻から一筋スーッと涙が流れ出したとお
もうと、後から後からあふれ出して、病みつかれて乱れた髪を濡らしたのでした。
死が近づいた頃、意識がはっきりしていたかどうかよくわかりません。濁った黄色い顔は浮腫を見せ、腹部は膨満し手や
足は限界と思われるほどに細くなっていました。二歳になったばかりの弟が、祖母と一緒にあいにきて、四ヶ月ぶりに見
る母がすっかり面変わりしているのを、不思議そうに見て近づくのをためらっていたのに気づいたかどうか。それでも「お
母さんにビスケットを食べさせてあげなさい。」と祖母に言われて、持っていたビスケットをおずおずと差し出した弟に、くち
びるをかすかに開けて、薄く目を開いたのでした。周りの人々が堪えきれずにむせび泣いたのを知っていたでしょうか。
北国の遅い桜も散った五月初めの朝早く、母は四十五歳の生涯を閉じたのでした。
ずいぶん長い間暗い日々が続いたように思います。母がおってもおらなくても、生活は平常通りに続けられていくのでし
た。嘆いたり悲しんだりして周囲の同情を受けることを私は好みませんでした。そんな強情な私を母はいつも困ったものだ
と思っていたみたいですけれど仕方がありません。家の人々、父や祖父母、叔父や叔母たちが、母を悲しいままに死なせ
てしまった敵のようにさえ思えたものですから、口を結んで我慢をするだけで過ごしていたのです。母に対しても、六人の
私たち兄妹を残して死んでいってしまったことは卑怯だなどと思ったのです。病気は仕方のないことでしたでしょうに・・・・
。十五歳の少女の示した反抗は、今にして思えば悲しみの裏返しなのでしょうけれど・・・。周りの人はわかってくれるわ
けはありません。ただ黙って見てくれているだけでした。
そんなある日、学校から帰って来た私がみたものは、母の祭壇の前に飾られた白い藤でした。大きな青磁の対の花瓶に
、嫋々と長い花房を垂らしているその姿は、庭の大木にからみついて咲いているのを遠目に見るのとは違って、心をうつ
ものでした。私はこの花が活けられたのをその日まで見たことがありませんでした。「藤の花は水をあげないものだと言う
ので、父さんがお酒をのませてたててあげたんですよ。私もはじめてみたのですよ。」と叔母がいいました。すると、そばに
いた父が呟くように「藤の花は母さんに似合うからな」と言ったのです。
藤の花は母さんに似合うと言う父、五月の風に揺れる藤の花房を見上げて、母が庭に佇んでいたことがあったのか、な
かったのかは確かに見たことはないのですけれど、私の思い出の中にそんな姿を見たことがあったように思います。父は
夕暮れ時のもの哀しさに包まれて、黙って立っていた母のさびしい姿をきっと知っていたのだろうと思います。
因習の多い旧家で、桎梏の中から抜け出せずにあきらめたように暮らしてきた父と母を、古い生活を打ち破る勇気がない
と言って責められるでしょうか。六人の子供たちの為にと、波風の立つのを怖れて堪えて来たのかも知れないのに。
こんな短い命ならば、もっと楽しく過ごさせてやりたかった。あのころもう少し早く気がつけば、死なせずにすんだのではな
かっただろうかなどと、父はきっと思っていたに違いないのです。水をあげにくい藤の花を、母さんには似合うからと言う理
由だけて、無理をして祭壇に飾った父の悔いと悲しみを、思いがけないほど強く私は感じたのでした。五月末のその日、
私は素直に泣いて、父と一緒に悲しんだのでした。
六人の子供と、旧家の維持の必要の為に、父は亡母の妹を妻に迎えました。私どもにとっては叔母にあたりますから、
何の血縁もない継母を持つよりはありがたいことなのでしたが、叔母の方から見るならば、この家の在り方や、母の生活
ぶりをよく知っているだけに、決心するまではどんなに苦しんだことでしょう。まだ充分に子を産み育てることの出来る年齢
だったのですが、継母は自分の子供をついに産みませんでした。そのことで、亡姉のあとを引き継ぐために嫁いできたと
言う悲壮なまでの決意を思わされるのです。
初めて叔母から母と言う名前にかわった日「母さん、今までどこに行っていたの?」と訊いた弟。それを聞いた周りのみ
んなが涙をこぼしたこと。亡母との思い出をどの人も持っているだけに、なにか悲しいような祝いの席だったことが忘れら
れません。
幾年かたちました。叔母はもうすっかり私どもの母になっておりました。祖父母も年老いましたし、時代もすっかりかわりま
したが、平穏な日々が続いておりました。.こうなるまでの叔母の苦労はどんなにか大変なことだったでしょう。兄も姉も
結婚して、私も世話をしてくれる人があって半月後には結婚式を挙げることになっておりました。あわただしい中にも父と
母はホッとしていたその頃でした。婚約者を訪ねて帰途についた頃から、季節はずれの颱風が吹き荒れて、列車がやっと
駅に帰り着いた時には、もうそこで運転休止になってしまうほどの烈風でした。屋根はめくれあがり、トタンがビュンビュン
飛んできますし、煙突は折れ、看板はたちまち板きれになって町の道を走って行ってしまうという状態で、恐ろしい有様で
した。やっとの事で帰り着いた家で私を待っていたのは、広い庭一杯に、奥の座敷すれすれのところまで、なって、すれす
れのところまでを占めて、あの塀の内側に立っていたシオジと、祖父がいつくしんでいた松の大木が横たわっている姿で
した。裏門の上に祖父が若い頃に書斎として使っていた離れも倒れていました。そしてあの白い藤の木も真っ二つに裂け
てしまっていたのでした。雨と風の中で、藤の木があげている泣き声を私は聞いていました。
それからの一週間、山子が来て藤蔓を切り、シオジと松を片づけて、庭隅に薪の山をこしらえました。すっかり整理がつく
と、大木を失った庭は精気をなくし、半分になった藤の木がやっとの思いで塀の外のシオジにつかまってたっているような
姿となって、ことさらに痛々しくみえたのでした。それでも、予定は予定で、うっすらと雪がつもった日、私の結婚式は行わ
れました。
二十日ぐらいして、祖父は脳溢血の発作を起こし、二週間病んで息をひきとりました。庭に積まれた風倒木の山を毎日黙
って見ていたと言う祖父。いつくしんできた大木の終焉と祖父の死の間に、何か関わりがあるように私は思ったのでした。
「裂けて駄目かと思っていた藤の木が芽吹いてきてくれました。また花をさかせることもあろうと思って喜んでいます」
母は私があの藤の木にどんな思い出をもっているかを知りません。半分に裂けた藤の木を見て悲しんだ私を慰めるような
手紙をくれたのでした。無惨な裂け目を見せて倒れていたあの藤の木が生き返ったと知ったときに、遠い日のあの思い出
をいっぱいにつけた白い花房がゆれている姿がよみがえりました。半分に裂けた藤の木が精一杯の力で芽吹いてきた姿
を想像することは胸の痛むことでしかなかったのです。
そして、八年、祖母も逝き、私のすぐ下の妹も嫁いで、兄も弟も上京して仕事についていましたから、実家には父と母と下
の妹の三人だけが静かに過ごしていました。大きな屋根を持つ家の中でたった三人の生活は静かですけれどさびしいも
のだったと思います。父も母もよく私たちに遊びに来るようにと言ってよこしました。「下の妹が嫁ぐについて、四人姉妹そ
ろって久しぶりにご飯を食べようではないか」と、父から便りをもらったのは、五月の中頃でした。「藤の花も盛りだからき
っと見にきなさいよ」と、母は私に付け加えました。そう言えば、半分になってから花の咲いた藤の木を見たことがなかっ
たのです。
姉と妹と連れだって実家へ行った日は、さわやかな風のわたるすばらしい好天でした。この空を白い藤の花房が揺れて
いるのだと想像すると心ときめく思いだったのです。
「今年はとてもよく花をつけたのよ。」と下の妹は言いましたけれど、説明出来ないほどの悲しみが私を打ちつけていまし
た。長い年月があの裂け目を少しはいやしてくれてはいたのですが、太い藤蔓には往時の艶めきはなく、ごつごつとした
木肌をさらしていました。何よりもシオジの木が一本しかないのですから、姿はすっかり変わってしまっていました。秋にも
冬にもこの藤の木を見たのですが、花の盛りの今ほどに哀れとは思いませんでした。五月の風は昔と同じようにさわやか
でしたし、咲いている花房もむしろ長く尾を引くようには見えたのですけれど・・・。私の頭の中にある藤の花盛りの姿は、
二本のシオジの木の梢までもはいのぼっているものでした。それはあまりにも鮮やかに残されている記憶でした。と、言う
よりも、年を重ねるごとにその美しさを増して行ったようなのです。現実の姿とは全く別のものになっていたのでした。
藤をいけさせたあの時から二十年、父の髪も白く薄くなっておりました。この木との過ぎ来し方も、今の母とかかわり合う
ものが多くなっていることでしょう。四人の娘を前にして、父も母もゆっくりと心を許しているようでした。
現実にあってきた悲しい藤の木の姿はもう今の私には思い出せなくなりました。そして四月、芽吹き始めたでありましょ
う藤の木は、私の頭の中で、二本のシオジの大木を梢まではいのぼっています。年ごとに老いてゆくはずのその姿は、思
い出の中にあるかぎり、年ごとに美しさをまし、花房は長く風に舞い、夏はシオジの葉としげりあって涼風をつくり、十一月
の空にはまたカラカラと実莢をはじいて、庭中に平べったい種子をまき散らしているのです。
終わり