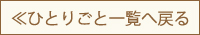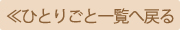小説を書いたら、特定のモデルはいないのに「あれはあの家のことでしょ?」「あの人のことでしょ?」などと聞かれることが多々ありました。
でも、事実をそのまま書いたのでは小説にはならない訳で、思い当たる人がいると言うことは、私のフィクションが現実味があると言うことで、まぁまぁ小説らしかったのかななどと思っていました。
その小説をあちこちに押しつけがましく送りつけて読んで貰ったら、恥ずかしいことに出版祝いだと言って、裂き織りの花瓶敷きを送って下さった方がいたのです。 裂き織りの暖かい色と手触りが、私を五十余年も前の暮らしを思い出させました。
田舎の昔の造りで、部屋数が無闇に多い家に私は育ちました。父母、祖父母、叔母が三人、兄妹六人に何人かの行儀見習いというのか、お手伝いさんがいて泊まり込みの若い衆が二人ばかりなどと言うホントに大家族でした。
部屋数が多いと言ってもその部屋を仕切っているのは障子や襖であり、座敷と呼ばれていた床の間のある部屋以外は、用途別に分けて使っていたわけではなく、夜になれば、土蔵の布団入れから布団を運び出してきて、みんなの寝室になります。そして一旦緩急あれば障子や襖を取り払い、大広間になると言う仕掛けでした。
集会場などのなかった時代ですから、嫁取りも弔いも法事もその大広間でと言うことになるのです。ですから、押入などと言う片づけに便利な設備はまったく着いていません。
そこで使う道具類も、その度毎に土蔵から運び出すのです。
一寸した来客があってお茶を出すなどと言うところ、今で言えば応接室のようなところは、通り抜けの庭の玄関に近いところにある部屋で、仕切られていない二十畳ほどの大部屋で、大きな柱時計がかかり、大きな囲炉裏があって、いつも鉄瓶が滾っていました。
祖父は上座と言っていたところにいつも座っていて、銀煙管で煙草を吸いながら家中に睨みをきかせていたのです。
誰でも出かけるときにはその端際に膝をついて「行って来るんし(行ってきます)」と、かえってきたら「今来たんし(ただ今)」と挨拶をしなければいけないのです。関所ですね。
乱暴に下駄を脱ぎ捨てたりすると「ちゃんと揃えて脱げ!」と関所の主の叱声が飛ぶという仕掛けです。
中の土蔵の前には台所があり、その広い板の間と十二畳ほどの部屋は、今風に言えばリビング・ダイニングルームでしょうか。食事をするテーブル(お膳でなかったのは田舎では少しモダン)が置かれてありました。
小さい頃はみんながいるこの部屋のテーブルの隅が宿題をする場所でした。お手伝いさんたちは板の間がたまり場で、 そこにおのおのの箱膳を並べて食事をし、縫い物をひろげたり、お茶をのんだりしていました。
人寄せをする大座敷の他に、奥の部屋という二間続きのへやがあり、床の間のついた方は父母の寝所でした。その二階の三間は私たちの勉強部屋として小さな机が並べられていました。
そこは夜になると叔母たちと布団をならべて寝る部屋なのです。2階の布団はさすがに土蔵には運ばずに部屋隅に積んでおかれました。土蔵に布団を運ばなかったのはこの2階と父母の寝所である奥の部屋だけでした。
祖父母は離れにいて、私たちはあまり出入りしませんでした。2階の私たちの布団はただ積んでおかれただけでしたが、父と母の布団には綺麗な裂き織りのカバーが掛けられてありました。父の布団には藍色を地色にしたもの、母のにはオレンジ色を地色にしたものだったと、今でも目に浮かんでくる鮮やかさです。
裂き織りの花瓶敷きを手にして、この布団にかけられたカバーに至るまで随分長いお話をしましたけれど、あの頃の暮らしが本当に懐かしく忘れがたいものだったからです。戦後、この大きな家もすっかり改造、改築をし整理されてしまいました。あのだだっ広い大広間もなくなって今は庭になりました。
母が逝って五十年、父も亡くなって二十年です。母の妹である叔母が継母として来てくれて、私たちを嫁がせてくれました。今では姪たち夫婦と子供たちが、この叔母だった母と一緒に住んでいます。
便利を考えた新しい構造の家です。押入もつけられ、土蔵に布団を運ぶこともなくなった暮らしです。あの頃は本当に昔話になりました。
裂き織りの花瓶敷きを見て思い出したあの父と母の裂き織りの布団カバーが今はどうなっているのかしらと確かめてみたくなって実家の母に電話をして聞きました。
「しまってあるよ。ホントに古くなって、ところどころ痛んでいるけれど・・・」
「ボロボロでもいいから貰えないかしら?」
「どうせ、今は誰も使わないし、他にも一枚あんまり痛んでないのがあるから、欲しかったらあげるよ」
花瓶敷きが発展してこんな嬉しいことになったのです。
その年、小学校の同期会があたので、出かけたついでに実家に行くと、母は早速取り出して来てくれました。
父と母の布団の上を覆っていた頃のやさしく匂いやかな色はすっかり褪せてしまっていました。
「これは自織りの紬だとか、銘仙だとかの着物の古くなったものを細く裂いて横糸にして織ったものだから、こんな風に大きなものを造ることが出来たと言うことは、そんな着物が沢山あった大家族だと言うことになるのよ。だから、この辺では裂き織りと言わずにボロ織りと呼んでいたものだった・・・。」
手触りはあまりしなやかなものではありません。これはやはり父や母が使ったように、敷物としたり、覆いにしたりして使うものだったのでしょう。
「年寄りの座ってする仕事として、お祖母さんなどが家族の着古した着物を丹念に解いて、それを細く裂いて、ちょうど毛糸の玉のようにし溜めて、充分と思われるほどの量になったら、少し縒りをかけて、麻糸を縦糸にして織ったものなのよ。ところどころ虫がついたように薄くなっているところは、毛もののメリンスみたいなのが混じっているせいかも知れないけれど・・・。今ではもうこんなものを織る人もいなくなってしまった。」
と母は言いました。
私の育つ頃はもう呉服商いが田舎の方にも店を張っていましたし、自分の家で機を織っていると言う記憶はありません。昔は自分の家で蚕を飼い、繭をとって、真綿にし、糸に紡いで自分の家の人々の着るものを織ったものだと祖母に聞いた記憶があります。
自家製の布は素人の製品だから、節が多くて「自織り」「節織り」などと言っていたそうです。見かけが悪いですが丈夫なものだったとも言っていました。
そんな風にして紡がれた布には、おそらく女たちの多くの思い出が一緒に紡ぎ込められていたと思います。そして、それが擦り切れてボロになっても、自分たちの暮らしや、子供たちの成長の記録のようなものだったのでしょう。
お歯黒をした老婆が、日がな一日ひっそりと座って布に織り込まれた限りもない年月を思いながら、細い裂き布にしてゆく仕事をする。想像すると涙ぐましいものがあります。
思い起こしてみれば、私たちも今のように物が豊富でなく、既製品なんかもあまりない時代に子供を育てましたから、裂き織りとまではとうてい行きませんが、セーターを編んでは着せ、小さくなれば解いて編み直しをし
てと言うことをするのがならいでした。
編み返す度に子供の成長を思い、過ぎ去った日々を思い出したりしたものでした。
深い思いをたっぷりと籠めて織り上げた布であれば、ボロになったからと言っても簡単には捨てられなかったでしょう。だから工夫をしてこのような敷物にして再利用することになったのでしょう。
もともとが、自織りの布でそれも普段着ですから、華やかな色は使われていなかった筈です。それに縒りをかけてありますから、まったく元の布の様子はわかりません。
縦糸とする麻糸に何色かの色を使っており、それが素朴で暖かい風合いを醸しだしているのです。
父と母の布団にかけられていたものは一尺ほどの反物の幅のものを三枚使っており、それには横糸にした細い裂き布の色にもそれなりのバランスをとっていて、織り手の布に対する愛情が伝わってくる。
家族の沢山の古着がこうして大きな敷物になるまで、祖母、曾祖母、そしてもっと昔の女たちは、きっと長い年月の思い出を織り込むために、機の前にすわったのでありましょう。
戴いたのは小さな花瓶敷き。それがどんな経緯で織られているのかは知りませんが、父と母の思い出につながり、祖母、曾祖母と昔の人々への思いにつながりました。母から貰ってきた古い裂き織りの布団の覆いはいつかテーブルセンターにでもしようかと思っています。
左右にスクロールしてご覧下さい